戯曲の豊かさ/映像の偏狭さ
日本劇作家協会が、2000年代に翻訳し出版した劇作のHow-to本、『現代戯曲の設計 劇作家はヴィジョンを持て!』(The Power of The Playwright’s Vision/ゴードン・ファレル/ブロンズ新社)を読んで、ガク然とした。

この本では劇作を、3つのヴィジョンと、8つのスタイルに分類する。
- 変化のヴィジョン
- リアリズム
- 叙事詩劇
- ブレヒト的叙事詩劇
- 不毛のヴィジョン
- 自然主義
- 不条理主義
- ロマン主義
- 神秘のヴィジョン
- 表現主義
- シュールレアリズム
シナリオ作法では、しばしば「主人公は変化せよ」と教わる。変化していないシナリオは、物語がわかっていないと断罪される。
しかし、この本の分類では、変化するのは、8スタイルのうち、3スタイルのみ。変化は少数派だ。
(不毛は不変化、神秘は説明不可、と定義される)
しかも、ブレヒト的叙事詩劇とは、異化効果により感情移入を排除したものだから、結局のところ、TVやハリウッド映画に代表されるシナリオのスタイルとは、「リアリズム」と「叙事詩劇」だけになる。映像で扱われるスタイルは、8つのうち、2つでしかないのだ。
8つのスタイルはほぼ均等にページが割かれ、感情移入と成長の物語は、この本の1/4で語られているに過ぎない。
たかだか100年の歴史の、通俗性を優先した、映像の限界だろうか。
5月と6月は、暇をみては、戯曲を読んでいた。日本劇作家協会新人戯曲賞の最終候補作を掲載した『優秀新人戯曲集』(ブロンズ新社)を10冊ほどと、『今日の英米演劇』全5巻(白水社/1968)。
さまざまな表現があり、ほっと気が楽になった。そこには2つのスタイルだけではなく、8つのスタイルがあったからだ。
日本のものでは、第17回日本劇作家協会新人戯曲賞を受賞した、柳井祥緒(やない さちお)さんの『花と魚』(2011)が良かった。
作・演出する劇団から出ている戯曲集に収録された、『獣のための倫理学』(2013)や『眠る羊』(2014)も、アニメやライトノベルを越えた先にある、エンターテイメントをつくりだそうとする意志が感じられた。
『ウルトラマンX』第10話「怪獣は動かない」は、『花と魚』と同じ世界観での話だ。
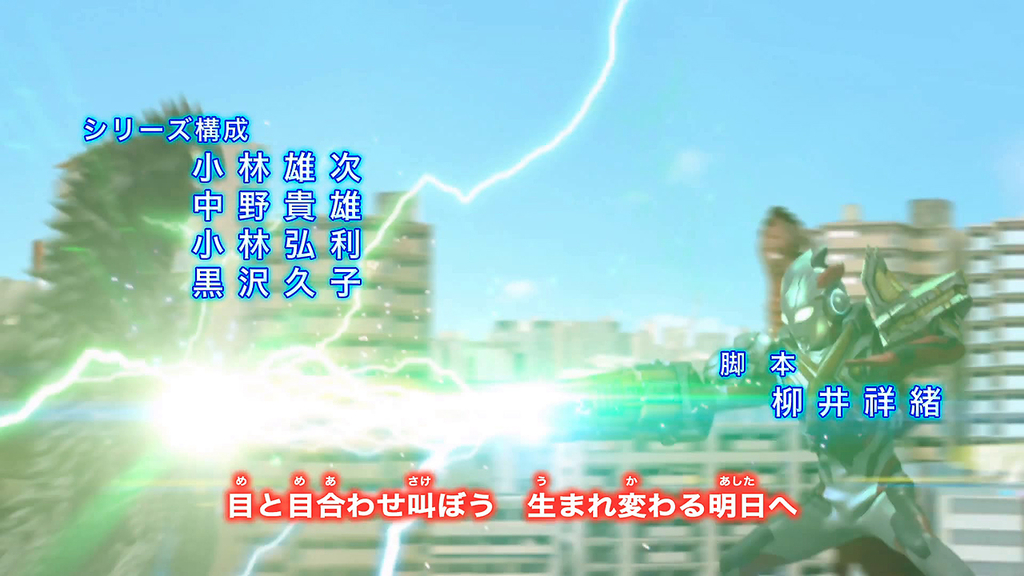
『今日の英米演劇』で気に入った戯曲は、どれも大御所のものだった。映画との関連を知って、自分の無知を恥じた。
ロバート・ボルト(1924-1995)
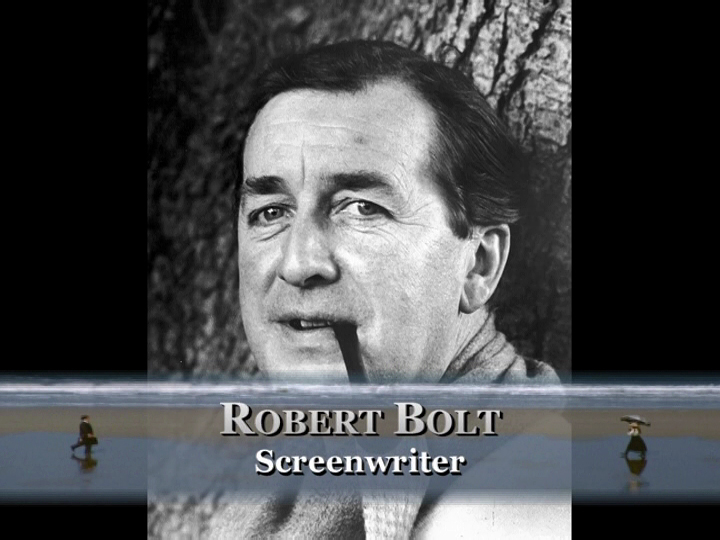
ロバート・ボルトは、『花咲くチェリー』(The Flowering Cherry/1957)や、『すべての季節の男』(A Man for All Seasons/1960)の、良質なストレートプレイに感心した。奇をてらおうとしない、誠実さがある。
このあと、デヴィッド・リーン監督と組み、『アラビアのロレンス』(1962)、『ドクトル・ジバゴ』(1965)、『ライアンの娘』(1970)と、脚本を連作。『すべての季節の男』を脚色した『わが命つきるとも』(監督:フレッド・ジンネマン/1966)、ロバート・デ・ニーロ主演の『ミッション』(監督:ローランド・ジョフィ/1986)と、どれも描かれる世界が壮大だ。
デヴィッド・リーン監督作では、『ライアンの娘』が、読んだ2本の戯曲に近く、ロバート・ボルトらしさを感じた。
ピーター・シェーファー(1926-2016)

ピーター・シェーファーは、『五重奏』(Five Finger Exercise/1954)、『ザ・ロイヤル・ハント・オブ・ザ・サン』(The Royal Hunt of the Sun/1964)、『ブラック・コメディ』(Black Comedy/1965)、『エクウス』(Equus/1973)、『アマデウス』(Amadeus/1979)を読んだ。
歴史上の人物を題材にしたものと、ドタバタコメディを、同じ作者かと思うほどに書き分ける “腕” に恐れ入った。『アマデウス』は両者の良いところ取りだ。私としては、『アマデウス』以前が、狙いを混乱したまま提出していて、大衆におもねっていない感じで、好きだ。
『他人の目』(The Public Eye/1962)がキャロル・リード監督・ミア・ファロー主演で『フォロー・ミー』(Follow Me!/1972)に、『エクウス』がシドニー・ルメット監督で映画化(1982)、そしてミロス・フォアマン監督で『アマデウス』(1984)と、組んだ監督もそうそうたるもの。
戯曲もシナリオも、構成の設計図が確固たる強度でつくられている。場ごとの展開や意図が、論理的で明解。
マーティン・マクドナー(1970-)

今の劇作家として、マーティン・マクドナーに注目している。映画『スリー・ビルボード』(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri/2017)のハズシかたや、ブラックなセンスは、定石をあえて拒否している。
去年に観た、ナショナル・シアター・ライヴの、『ハングメン』(Hangmen/2015)も独特な、苦い笑いの、記憶に残るラストだった。
日本語訳のある、『ウィー・トーマス』(The Lieutenant of Inishmore/2001)と、『ピローマン』(The Pillowman/2003)も、熱情と悪意に満ちたヒドイ話で、褒め言葉として「最低ッ!!」だった。

余白があったり、結論を出さなかったり、不条理をわからないまま提出したり、つくりものとしてのネタを割ったり、……演劇の持つ表現の豊かさに、映画は追いつくことができるのだろうか。
【追記】ハヤカワ演劇文庫『動物園物語/ヴァージニア・ウルフなんかこわくない』の解説で、一ノ瀬和夫さんが、エドワード・オールビーの “プロットをつくらない” 件を記している。
当時のアメリカのリアリズム劇には、表現上の写実主義とは別に、イデオロギーとしての因果律が、鉄則のごとく前提されていた。一切の出来事には必ず原因がある。こうなると必然的に物語は予定調和的な構造に傾斜していく。つまり、リアリズムと名乗ってはいても、物語は観客や読者の因果律意識の枠のなかで展開し収束する。往々にして辻褄合わせ的になり、リアリズムという言葉とは矛盾する。むしろ、作り物的な構造を内包するものになる。
《リアリズム》vs.《原因と結果》の二律背反として、興味深い。すごく、腑に落ちた。